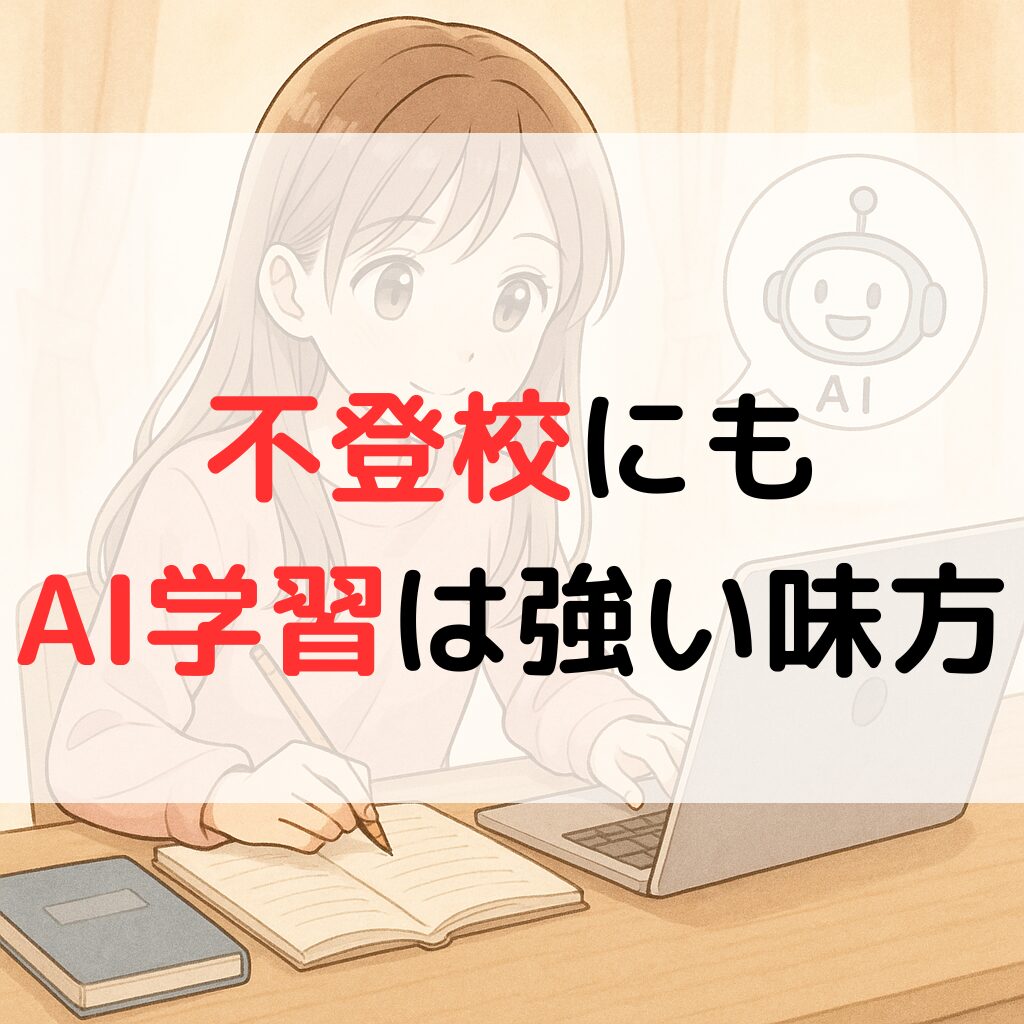執筆:岡田
「今日も学校休むの?」と声をかけたあの朝、私の心には大きな不安がありました。
起立性調節障害で、布団から出られずに泣く娘の姿を見て、「どうすればこの子の力になれるんだろう」と、何度も自分に問いかけました。
自宅での学習を始めましたが、教科ごとに進めるのは想像以上に難しく、親がすべてをカバーすることの限界を痛感しました。特に、毎日のモチベーションを保つことがとても大変でした。
そんなある日、SNSで「AI学習ツールで子どもが前向きになった」という記事を目にし、すぐに無料体験を申し込んでみました。
最初は疑いの目を向けていた娘も、自分の好きな単元から気軽に取り組める点が安心材料になったようで、次第に前向きな表情が見られるようになりました。
AIは、子どもの学びをサポートする心強いツールです。 ただし、それだけに頼るのではなく、「今日はこれをやってみようか」と親子で声をかけ合いながら進めるスタイルが、子どもの意欲を高めてくれます。
本記事では、私たち家族の実体験をもとに、不登校のお子さんを持つご家庭が前向きに自宅学習を進めるためのヒントをお伝えします。
不登校と向き合う家庭が増える今、親ができることとは?

ここ数年、不登校の児童・生徒の数は増加傾向にあります。背景には、人間関係のストレスや発達特性、繊細な気質(HSP)など、多様な理由が絡み合っているのが現状です。
その背景には、人間関係のストレスや発達特性、繊細な気質(HSP)など、多様な理由が絡み合っているのが現状です。
私自身も、最初は「どうすればいいのか」と判断がつかず、夜遅くまでスマホを手に調べ続けたことを今でも覚えています。「私たちだけじゃないんだ」と気持ちが少し楽になったこともありました。
時間が経った今だからこそ思うのです。一番大切なのは、目の前にいる子どもの気持ちに寄り添い、受け止める姿勢なのだと。
現代の子どもは“学びたい”気持ちを諦めていない

不登校の子どもたちと関わって感じるのは、「学ぶことが嫌になったわけではない」という事実です。

私の娘は、「算数は遅れたくない」「ピアノは続けたい」と口にしてくれたことがありました。また、「周りと同じスピードじゃなくても、自分のペースで学びたい」と自分の思いを伝えてくれたことで、我が子に対するサポートの方向性を考えるようになりました。
この言葉をきっかけに、私たちは家庭で安心して学べる環境づくりを始めました。時間に縛られず、体調や気持ちに合わせて学習ができるAI学習ツールを取り入れたことで、少しずつ「やってみようかな」という前向きな気持ちが芽生えてきたのです。
AI学習ツールが自宅学習の救世主になる理由
不登校のお子さんが無理なく学びを続けるために、近年注目されているのがAIを活用した家庭学習ツールです。
個別最適化された学びで「置いていかれない安心感」
学校の授業はどうしても集団を前提にしたペースで進みますが、不登校の子どもにとってはそれが精神的な負担になることがあります。そんなときに活躍するのが、AIツールの柔軟なカスタマイズ性です。
-
スタディサプリ: 娘は「5年生の内容をもう一度見直したい」と自分で選び、苦手な部分を繰り返し学び直していました。私は「何度でも繰り返しできるよ」と声をかけながら見守っていました。 「授業に遅れている」と感じていた娘も、少しずつ「大丈夫かも」と前向きな気持ちを取り戻せたのは、こうした個別最適な学習のおかげだと思っています。
-
ChatGPT: 「地球はなぜ丸いの?」というような素朴な疑問にもすぐ答えてくれて、子どもの「知りたい」という気持ちをそのまま学びにつなげることができます。
自己肯定感を育むAIのサポート
AIのメリットは「学力アップ」だけではありません。自分のペースで学ぶことで得られる達成感が、子どもの自己肯定感を育む点にも注目すべきです。

娘は、自分の作文をChatGPTに見せて「この表現は素敵ですね」という返答をもらったとき、「自分の文章も褒めてもらえる」と嬉しそうにしていました。失敗や間違いに対しても、「次のステップに活かせるね」と肯定的なフィードバックをくれることで、“間違えてもいい”という安心感を持てたようです。
実際の事例|不登校から大学受験へ。AIが切り開いた未来

AIの力は、学びに前向きになれない子どもたちに寄り添い、「学ぶ楽しさ」を思い出させてくれる強力な支援ツールです。ここでは、私の娘がどのようにAI学習ツールを活用し、大学受験を乗り越えたのか、その具体的な道のりをお伝えします。
私の娘(起立性調節障害)の場合
娘は小学6年から中学時代にかけて、体調の波が激しい起立性調節障害で登校が難しくなりました。午前中は起き上がれず、教科書を開くだけでも苦しい日々が続きました。
その状況を少しでも前向きにしようと、我が家ではスタディサプリとChatGPTの導入を決意。 午後から短時間の学習を娘と一緒に取り入れ、「ここまでやれたね」と小さな達成感を大事にする工夫を重ねました。
-
スタディサプリで基礎を固める: 中学2年生になった頃、「大学に行きたい」という強い意志を娘が示してくれました。しかし、授業のブランクが大きく、どこから手をつければいいかわからない状況でした。 そこで娘が自ら選んだのが、スタディサプリの「高校講座」です。彼女は中学の復習から始 め、高校の学習内容を自分のペースで進めました。 特に、苦手だった数学は、理解できるまで何度も同じ動画を見返していました。
-
ChatGPTを学習の伴走者に: 英文法や現代文の読解でつまずいたときは、ChatGPTに質問を投げかけました。まるで家庭教師のように、理解度に合わせて分かりやすく説明してくれるため、娘は誰にも気兼ねなく質問を繰り返すことができました。 また、小論文の練習では、ChatGPTに添削を依頼し、より論理的な文章構成を学ぶことができました。
不登校だからといって、学ぶ力がなくなったわけではありません。 必要なのは、プレッシャーを与えず、自分のペースで安心して学べる場所です。AIツールは、その環境づくりを大きく後押ししてくれると実感しています。
親としての関わり方|AIに「任せきり」にしない工夫

AIツールは、自宅学習を効率的に進められる便利な存在です。けれども、「AIがあるから安心」と親が手を引いてしまうと、子どもは孤立感を抱きやすく、やる気をなくしてしまうことがあります。

私も最初は「AIがいれば一人でできるはず」と思い込んで、娘に任せきりにしていました。ですが、数日後に娘がぽつりと「ひとりじゃやりたくない」と私に言いました。その一言で考えを改め、“共に学ぶ時間”を作るようになりました。
結果よりも「取り組む姿勢」を認めることが自信につながる
AI学習は、マイペースで進められる反面、すぐに目に見える成果が出るとは限りません。だからこそ、毎日のちょっとした努力に目を向けることが大切です。
「今日は5分だけど机に向かえたね」「昨日よりも1問多くやってみたね」など、小さな一歩をしっかりと褒める習慣が、やる気につながります。「ちゃんと見てるよ」「頑張ってるね」と声をかけることで、子どもは“自分の努力が認められている”と感じ、前向きな気持ちが育ちます。
まとめ|AIを活用して、もっとラクに楽しく育児しよう
「学校に行けない=学べない」時代は、すでに終わりを迎えています。AIを活用することで、自分に合った学びのスタイルを選べる環境が整ってきています。
親と子、そしてAIで築く新しい学びのかたち
AIの進化によって、親の関わり方もこれまでと変わってきています。「任せる部分は任せる」「見守るときは見守る」「必要なときはしっかり寄り添う」――この絶妙なバランスこそが、子どもに安心感を与え、やる気を育てます。
AIは「親子の学びを支えるパートナー」
娘が「AI先生に褒められた!」と笑顔で話す姿を見るたび、AIを取り入れて本当によかったと感じます。不登校の時期もありましたが、私たちが共に見つけた新しい学びの形は、かけがえのない経験になりました。
今、同じように悩んでいるご家庭にも、AIの力を上手に使うことで、「学ぶ力」を無理なく育てる道があると伝えたいです。焦らず、親子で一歩ずつ。AIと共に進むこの道は、きっとその子らしい未来へとつながっていきます。